7月19日(土)、有機稲作講座の第7回目を開催しました。
この日は稲の生育に関するビデオ学習の後、田んぼで実際に稲を観察し、獣害対策についても学びました。
最初に、稲の生育に関するビデオを視聴しました。稲の生態は知らないことばかりで興味深いですが、なかなか専門的で難しい内容もありました。
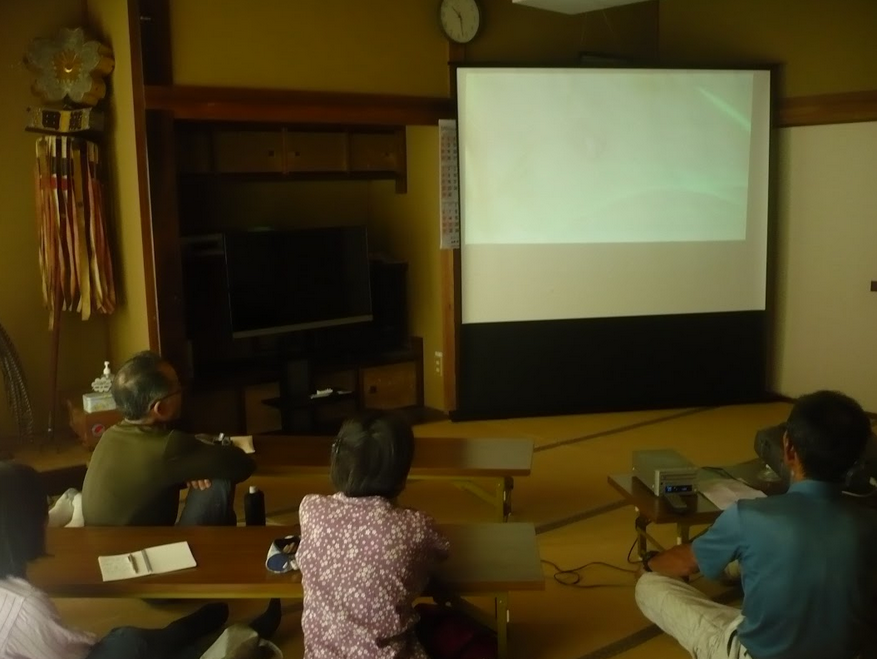
その後、田んぼに移動して、実際に稲や田んぼの様子を観察しました。
現地ではまず、獣害対策について話を聞きました。山に囲まれたこの田んぼの周辺では毎年イノシシが出ます。当初は講座で電柵を張る実技を予定していましたが、その前に田んぼにイノシシが入ったため、講座の日を待たずに電柵を張りました。イノシシ対策は待ったなしですが、実際に狩猟を行っている人はほんの一握り。獣害は増えるばかりだと言います。

その後、田んぼをぐるりと回り、穂が出てきている稲の様子や、イノシシの入った形跡、ザリガニが稲を切った跡、外来種の雑草、稲の花が咲いている様子などを観察しました。花と言っても、花びらがあるわけではなく、白く見えているのは稲の雄しべです。とても小さく、遠目では見えないサイズです。


観察が終わると、別の田んぼに移動して、田んぼごとの様子の違いを観察しました。同じように育てていても、田んぼ一枚一枚、様子が異なります。草が出てしまった田んぼは葉の色が薄くなっています。「品質に影響は出るのか?」「味は変わるのか?」受講生から様々な質問が出ていました。

最後に自分たちで植えた田んぼを見に行きました。植えた時、とても小さかった苗がここまで育ったことを喜びつつ、皆さん、じっくり観察していました。

真夏のこの季節は、ほっと一息ついて、座学の時間が取れる時期でもあります。座学と実技を合わせて、学びを深めていきたいですね。
