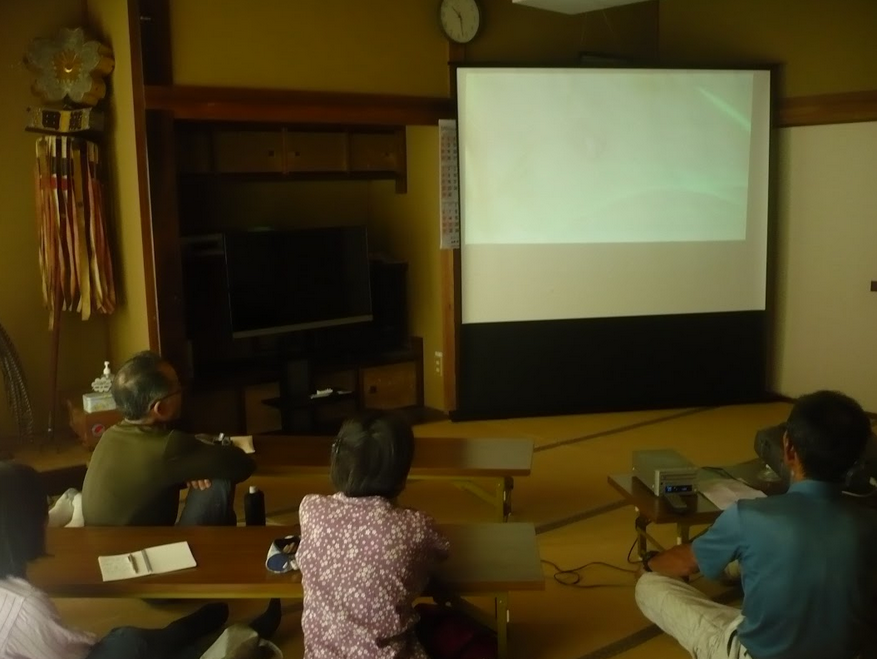9月13日(土)、有機稲作講座の第8回目を開催しました。
今回はいよいよ稲作のクライマックスとも言える稲刈りです。現在ではコンバインで刈って機械乾燥するのが一般的ですが、今回の講座ではバインダーという小さな機械で稲刈りをして、天日干しを行います。
この日は前日に大雨が降ってしまい、田んぼに水が貯まっていました。風も吹いたので、稲も斜めに倒れ気味です。田んぼのコンディションとしては、少々難易度の高い稲刈りです。
最初に、手刈りをして束ねる方法を学びました。機械で刈る場合でも、田んぼの四隅は手で刈る必要があります。講師のデモンストレーションの後、さっそくみんなで刈っていきます。


次に、バインダーにオイルをさす方法を学びました。機械整備の方法を知ることも欠かせない知識の一つです。

バインダーの準備が整ったら、いよいよ実際に稲を刈っていきます。講師のデモンストレーションの後、一人ずつ、説明を受けながら使っていきます。実際に刈っていく中で、「まっすぐ田植えするのが大事なんですね!」と、田植えのできが稲刈りのやり易さに直結してくるという気づきもあったようです。


稲を刈りおえたら、次は稲を干すための骨組みである「ならし」を立てます。この地域では「ならし」ですが、「稲架(はざ、はさ)」など、地域によってさまざまな呼び名があります。
この「ならし」、実際に立ててみると、これがなかなか難しい!細かいコツがいろいろあって、この講座の中だけでは全てを伝えきれないので、それは今後、各自が経験を積みながら学んでいくことになります。

ならしを立てたら、今度は先ほど刈った稲を掛けていきます。「今日みんなで刈った1列分は完成させたいね!」ということで、スピードアップして、ならしを立て、稲を掛けていきます。


蒸し暑く、足元もぬかるんで大変なコンディションでしたが、無事、講座の時間内に1列完成させることができました。
次回は脱穀。2週間後を予定していますが、脱穀はお天気次第でできるか決まるので、お天気に恵まれることを祈っています。